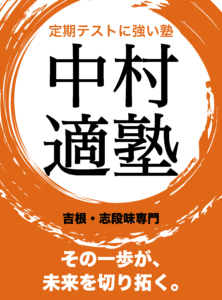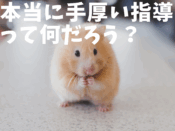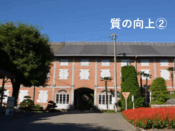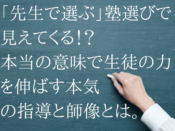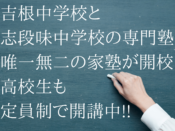手厚い指導の真意②

高校生になると中学生の頃よりも勉強時間を作るのが大変になります。
勉強内容も中学生のときよりも膨大になるため、
いわゆる「ドリル形式」で大量の問題を解く中で習得する方法が大きな負担になってきます。
そもそも高校生の場合は気の利いたドリル形式のプリントがすべての科目で存在するわけでもありません。
そうなると、
どうやって勉強すればいいのかもわからなくなり生徒たちは路頭に迷うわけです。
高校生になると急に成績が下がってしまう現象がありますが、
あの現象のすべてが高校の先生の責任にあるとするのはかわいそうな話です。
おそらくほとんどの高校生は、
中学生のころに物量作戦の中毒になっています。
私自身も常に気を付けている点です。
生徒の追い込まれ具合や残りの限られた勉強時間を考えるとやむを得ない状況がありますが、
なるべく「手段の工夫」を生徒に身につけてもらうのが基本方針です。
中学生を対象にした塾によくあることですが、
生徒が高校生になった後のことを考えていないからかもしれません。
この論争はSNS上でも度々繰り返されていますので興味がある人はぜひ調べてみてください。
(とはいえほとんどの高校生が高校の勉強に打ちのめされる現実がありますけどね。。。)
一つのテキストや参考書をこれでもかと使い尽くす勉強がおすすめです。
初見の問題がないように全パターンを網羅しようとする勉強は無理がきます。
大量の問題を解きまくるだけの方法も、
それでは自分の脳を使っているとは言えないでしょう。
基本的な問題でも、
その一つ一つを絞り切るかのように何度も何度も解き、
研究するかのように分析していくことで本当の意味で理解が深まります。
間違えた問題や解けなかった問題は最低でも3回は解き直しましょう。
知らなかった知識は教科書や辞書を引きましょう。
その中で自分の弱点だけでなく、逆に強みも見えてくるものです。
(次回へ続く)